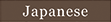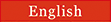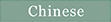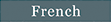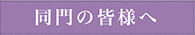桜餅の意味と地域の違い
3月や4月ごろの桜が咲く季節に食べることの多い桜餅ですが、皆さんは桜餅を食べましたか。
桜餅は何を表しているのか、地域によって違いがあるのはご存じでしょうか。
今回は桜餅の意味や関西と関東では桜餅はどのように違うのかについて紹介していきます。
桜餅の意味
桜餅は春の訪れを教えてくれるものであり、ピンク色は桜の花を表していてお花見の季節が来ることを楽しみにする気持ちを表しているそうです。

桜餅は江戸時代からあります。
江戸時代の頃からずっと人々は春が来て桜が咲くのを楽しみにしていたのですね。
また、桜餅はピンク色をしていて食卓に並ぶと華やかになることなどから、ひな祭りのときに食べる方も多いそうです。
関西と関東の違い
桜餅は関西と関東で形や生地が異なります。
関西風の桜餅は「道明寺」とも呼ばれているそうです。
その理由は道明寺粉を使っているからです。
道明寺粉と言っていますが完全な粉の状態ではなくもち米が原料ため、お米の形が少し残っています。
なので、ふっくら、もちもちとした食感です。

中にはあんこが入っており、塩漬けされた桜の葉で巻かれているのが特徴です。
一方で、関東の桜餅についてですが、関東の桜餅は「長明寺餅」と言われているそうです。
関西の桜餅と原料が違い、小麦粉が使われているそうです。
小麦粉を使った生地を薄くのばし、あんこをくるんだものになります。

関西の桜餅と同じところは、塩漬けにした桜の葉で巻かれていることです。
このように関西と関東では桜餅と言っても見た目や食感が全然違います。
現在は関西の桜餅が全国的に主流になっているようです。
そのため、関東の桜餅を食べたことのない方が多いと思いますが実際に食べてみて何が違うのか確かめてみてください。
煎茶道ではお茶席で一煎目と二煎目の間に練り切りなどのお菓子を食べます。
そのようにお茶を飲むときに一緒に食べるお菓子としてこの季節は桜餅を食べてみてはどうでしょうか。
桜餅だけでなく一年を通して季節に合わせたお菓子を楽しめたらいいですね。