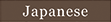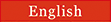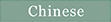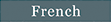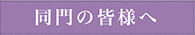桜の歴史
日本の国花でもあり、お花見や御雛飾りなどで私たちの生活にも身近な存在である「桜」ですが、その歴史はいつ頃から始まったのでしょうか。
桜が日本人にとって身近な存在になったのは、平安時代頃のようです。
それまでは、中国から持ち込まれた梅や桃が、貴族社会で珍重されていました。
しかし、平安時代になり国風文化が流行したことをきっかけに、山の神が宿る桜を愛でる風潮が広まりました。
3月3日の桃の節句は、もともと中国から伝わった文化で、春の訪れを祝い無病息災を願う「上巳の節句」という儀式でした。
この儀式では、もともと中国から持ち込まれた観賞用の植物である、桃や梅を使用していましたが、平安時代になると時代の流れとともに、桜を用いるようになりました。

また、古文や和歌において「花」というと桜をさしますが、これも平安時代の有名な和歌集である「古今和歌集」から始まりました。
奈良時代の万葉集にも桜を詠んだ和歌はあるようですが、春の花の象徴として詠まれるようになったのはやはり、古今和歌集からのようです。
桜の代名詞ともいえる「染井吉野」は、染井村という地名が由来だそうです。
江戸時代頃、染井村には多くの植木職人がおり、そこでつ接ぎ木苗が作られたと考えられています。
染井吉野は成長速度が特に早く、美しく大きな花が多くつくため、全国に広まりました。

江戸時代の人々が見ていた桜ですが、現代を生きる私たち、そして未来を生きる人々も同じ桜を見るのだと思うと、悠久の時を感じさせられ、ますます桜の魅力を感じます。
芸術にも桜は影響を与えており、江戸時代に流行した浮世絵で有名な、歌川広重の「名所江戸百景」や、葛飾北斎の「富嶽三十六景」にも、庶民が花見を楽しむ様子が描かれています。

桜の花言葉には、「精神の美」というのがあるそうで、日本人の品格を表しています。
咲いている時間が短く、見惚れているうちに散ってしまう儚さが、私たちを魅了していると感じます。

煎茶会で用いられる文人華には、国花である春の桜と秋の菊を合わせて「万代長寿」という弥栄の繁栄を表す雅題があります。
先人たちが花に託した思いや願いを大切に受け継がれてきた煎茶道や日本文化には、視覚だけではない心の美しさも感じますね。