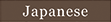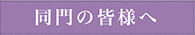雰囲気を楽しむこと

お茶席に欠かせないものは様々にありますが、その一つに「お花」があります。
お部屋の床の間に飾られたり、お客様の座る位置に飾られたり。
また、茶道具の棚の上に飾られることもあります。お花が飾られるのはお茶席だけではありません。
読者の方の中にもお家にお花を飾る習慣がある方もいらっしゃるでしょう。
また、花を愛でるのは日本の文化に特有という訳ではありません。
例えば、西洋の絵画にも古くから花が描かれていることや、ローマ神話にフローラという花と春を司る神が登場することなどからもわかるでしょう。
では、日本の花の愛で方と西洋の愛で方が同じであるかというと、どうも違いがあるようです。
西洋でよく愛でられている花の例として、ここではバラとチューリップをあげてみたいと思います。
バラというと私はシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』の「私たちがバラと呼んでいるあの花の、名前がなんと変ろうとも、薫りに違いはないはず」という有名な箇所を思い出します。
人の美しさの比喩としてバラが使われます。では、チューリップはというとオランダの「チューリップ・バブル」などを思い出します。
オランダ黄金期にはチューリップの球根の売買で巨万の富が行き交いました。
このように古くから多くの西洋人を魅了してきたバラとチューリップ、二つの花に共通することは「一輪で成り立つ花」であることではないでしょうか。
ではそういった花々が日本で愛でられていないのかというとそうではないでしょう。
「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」という言葉があるように、日本では、この3つの花などが「一輪で成り立つ花」の代表格でしょう。
しかし、日本ではそういう花だけが愛でられているのではありません。
桜や梅がその代表格です。木にたくさんの小さな花が一度に咲くというような種類の花が、ごく一般的に愛でられます。桜などの美しさは群生しているのです。
こういった美しさを感じ取る感性は、西洋にはない感性ではないでしょうか。
単体ではなく全体を抱擁するような美の感覚。これは日本特有のものだと思えます。
こういった日本の美的感覚は宗教観にも繋がっているかもしれません。
「八百万の神」という世界観が日本固有の宗教である神道にはありますが、「そこかしこに美の一片が散見されるが、それらが総体となって美しい雰囲気を醸し出す。」という世界観は「八百万の神」の世界観とリンクするところがあるのではないでしょうか。

例えば、桜が咲いている情景を思い浮かべてみてください。桜並木が薄ピンク色のトンネルを作っている情景を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
その情景の美しさは総体としての美しさだということができるでしょう。一つ一つの花の実態は全体像からは掴めません。
しかし、その不確実な美に身を委ねて、全体を俯瞰することで初めてその総体としての美しさを感受できるのです。
普段の生活では、つい不安になってしまって実態とか真実とかを追い求めそうになることがありますが、そんな肩肘張っていたら感じ取れない次元というのが世の中にはあるようです。

また、桜の花を愛でているとき、本当に私たちはその花自体を愛でているのでしょうか。実は、その桜を咲かせている春を愛でているということはありませんか?
寒くて暗い冬の季節が終わり、花々の咲き乱れる明るい春という季節がやってきた。
その象徴としての桜を愛でることで春の到来を賛美している。という側面が桜の美には抱擁されているようにも思えます。
『新古今集』の藤原長家の歌に、
「花の色にあまぎる霞たちまよひ空さへにほふ山桜哉」
というものがありますが、霞も桜の美しさと一緒になって情景全体の美しさを醸し出している様子が目に浮かびます。
日本には雰囲気を愛でるという姿勢が独特のものとして伝統的にあるようです。
雰囲気を愛でることは、花を見るときにしかないものではないでしょう。
お茶にもこの姿勢は見られるように思います。
お部屋の設えから同席者の所作まで全ての要素を雰囲気として感じながら楽しむ、というのがお茶なのかもしれません。
そんな心に余裕のある感性を磨いていきたいものですね。

参考文献
佐々木健一『日本的感性:触覚とずらしの構造』、中公新書、2010年.
シェイクスピア『ロミオとジュリエット』、中野好夫訳、新潮社、1996年.